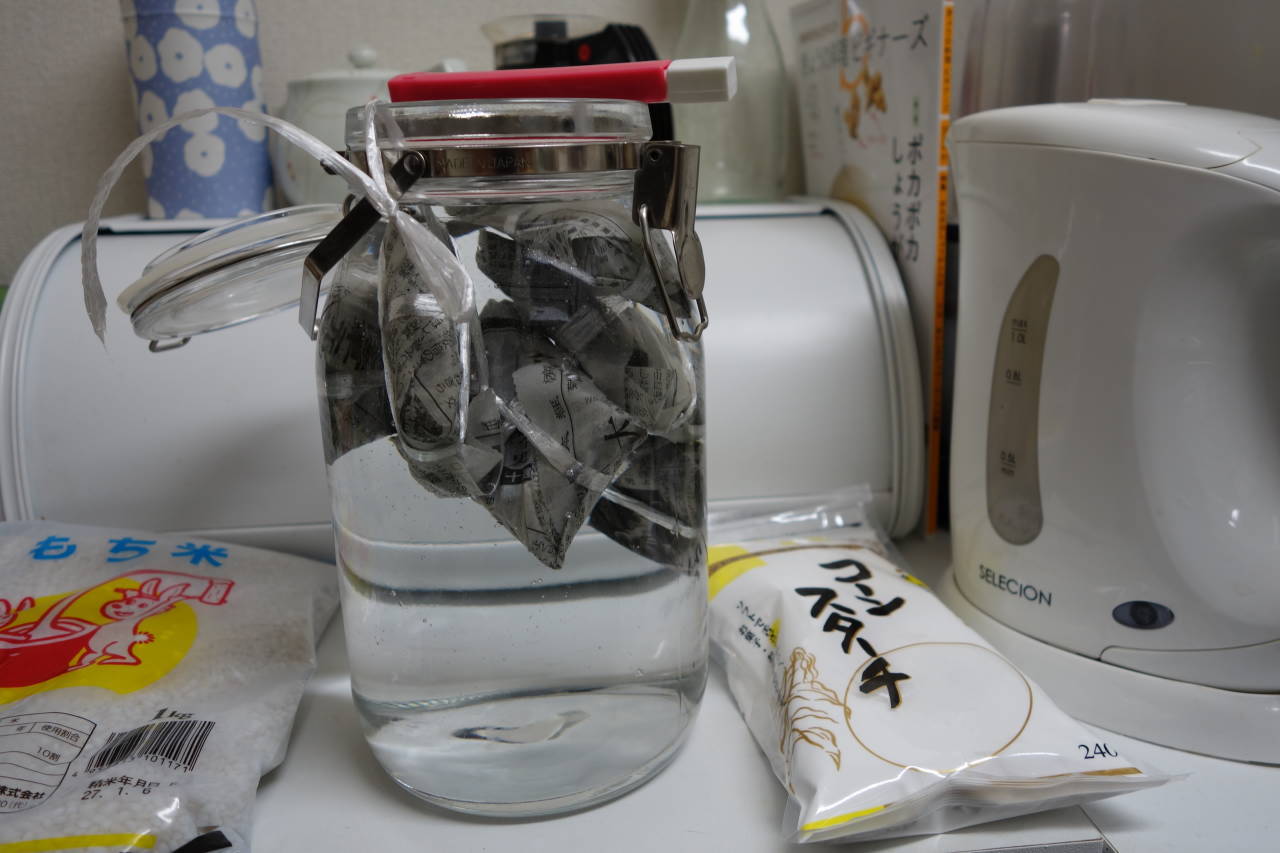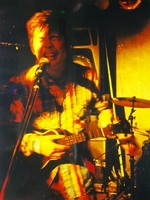デイジー☆どぶゆきの新作『
ナツアカネ』

1曲目『虹を描こう』の冒頭「ラララ...」の歌声が聞こえた瞬間、これまでの作品とは位相の違う音だと気付く。
一言で表現するならば「モノラル」ではない「ステレオ」のデイジー☆どぶゆきである。
もちろん実際の録音をモノラルでしたと言うことでは無く、伝えられる音楽の位相において。
圧倒的なライブパフォーマンスの氏。ライブにこそどぶゆきの真骨頂がある。
一方でスタジオアルバムはライブを切り取る事ではなく、ライブではできないことを徹底的に作りこむことによって送り出されてきた。
普段ライブでの構成は基本はどぶゆき(Vo. Uke)で、バンドを組んでいたころはバンドメンバー、ソロになってからはスポットでのサポートメンバーが1~2名つく程度。当然できることも音の数も限られる。
一方レコーディングであれば無限大にバリエーションが可能になる。人数も構成も自由。
そうやって作られてきていた。
今回も同じ手法であるのだが、明らかに位相が違う。
その理由について考える前に氏の過去の作品でどのように作りこみが行われてきたかを振り返ってみたい。
『手づかみの風』
プラグ・デイジー時代の作品。
ここ作品ではてっこ(チェロ)という強烈な個性がデイジーと並び立っている。
リードボーカルも楽曲提供もデイジーなのだけれど、てっこのチェロやコーラスは私が主役だといわんばかりである。
音の大きさやアレンジにもてっこの意向が強く反映しているように思われる。
たとえば『デイジー・マーチ』は氏の愛称が曲名に入っているにもかかわらずてっこのチェロとスキャットが主役だ。
『なつくさ』での「おんころころ」や「はいーやさーさ」と念じるところなんかも。
ややもすればデイジーが消されてしまうが氏も負けじと主張する。
そして二人がせめぎ合うことで化学反応が生まれている。
たとえば「スター・カマロ」の歌い出しで「Yeah」を重ね合わせるところ。
それでいてとっ散らかっていないのは、二人が当時持っていた音楽性のようなもの:アコースティック楽器、哀愁、郷愁、がそれほど離れていなかったからだろう。
『グレープフルーツムーン』『特急ダディ』
てっこと袂を分かつことになりソロ名義で活動を始めた氏だが、傍らには常にベーシスト、ポマードマンがいた。
このポマードマン、前面に出る性格ではないがデイジーの特徴をよく知り、氏の良さを引き出すサポートをしている。
例えば『レレ・ハッピーデイ』『流星群の夜』ではサスティーンの短いウクレレの隙間を絶妙に埋めているし、『しんかんせんのうた』では「はやい」「おそい」の二言で見事に愉快で間抜けな楽曲に仕立てている。
当時、氏はポマードマンを「素晴らしい僕の舞台装置」と呼んでいた。
まさにその通りで、ポマードマンが舞台装置としての役回りを果たしているからこそ、2人の共演で成立する音楽でありながらソロ名義として納得できる作品となりえた。
『太陽の瞳、夜蛾の唄』
諸事情でポマードが脱退。
完全にソロとなった氏が試行錯誤の末作り上げた前作である。
ここで氏は手持ちのアイデア(曲想、主題、歌詞、奏法、楽器構成etc)をこれでもか、これでもかと詰め込んでいる。
自身の陰と陽を示すかのような『太陽の子』『ミズアオ』、おそらくわが子の事を歌っていると思われる『ぼくのこせんきょう』、エンターテイナー・どぶ
ゆきの極致ともいえる『ハイブリッド・ラヴァー』、そしてルーツを語る『古鼠川唄』。
全曲で複数のウクレレ、自身の歌に加え様々な音を添えて、曲によっては自身の歌やウクレレ演奏を抜いてまで自身の曲想を具現化せんとしている。
脳内にあるどぶゆきバンドの具現化。まさにウクレレ歌唄いの面目躍如である。
さて、『ナツアカネ』である。
12曲中、新曲が8曲(うち1曲はバージョン違い)で再録が4曲。
インスト含め、どの作品も素晴らしい歌である。
しかしながら冒頭で述べた通り、音の位相がこれまでと違う。
可能な限り定量的な説明をするのであれば、音が今までよりもはるかに多い。
これまでの作品は音楽好きの少年が集まってワーワー言っている、いわばスキッフルバンドのような雰囲気だった。
音の少なさは物足りなさかもしれないが反面一つ一つの音が鮮明になる。
だからデイジーも、てっこも、ポマードマンも、はっきり見えた。
その意味でモノラル的だった。
一方今回の作品は腕のあるホーンセクションが大幅に参加したリズム&ブルーズであり、ビッグバンドのようだ。
氏の楽曲が非常にバラエティに富んだ音で見事に彩られ、飾り立てられている。
沢山の音が響いている。だからステレオなのである。
聞けば今回、第一線で活躍する素晴らしい方がアレンジャーとして参加していると聞く。そのお蔭なのだろう、
今回はデイジーの個性に何かをぶつけて化学反応を起こすものでも、あるいはうまく惹きたてるというものでもなく、
氏の個性をキーデバイスとしつつも他のツールも積極的に活用し全体のパッケージとしてよい作品に仕上がっている。
だからなのだろうか、どの曲も聴くものを祝福するかのような暖かさに満ちている。
新録である『虹を描こう』『オモエサンライズ』は希望にあふれ『ナツアカネ』『浜に咲く』は哀しくも先を感じさせる余韻に満ちている。
また氏の作品は大抵各曲ごとに曲調の明暗がはっきりしていたものだが、今回はそれが薄い。
再録の曲を聴き比べるとはっきりとわかる。
例えば『特急ダディ』では暗に傾いていた『ハマナスのブルー』が明らかに暖かさを帯びているし、『しんかんせんのうた』からはアンダーグランドな間抜けさが程よく薄まっている。結果として誰にでも聴きやすい作品となっている。
明暗のはっきりしたどぶゆきの個性に何かをぶつけるわけでも無く、かといって前面に押し出すのではなく、どぶゆきを用いて誰もが暖かみを感じる作風へ。
この変化をどう感じるか、昔からのファンには賛否両論あるだろう。
ただ以前からデイジー☆どぶゆきは「ウクレレ音楽」という枠に留まる事を嫌い、歌唄いとして世に広く響くブルーズを出さんとしていた。
また震災後の活動を経て、音楽がいかに人に寄り添うのかについて考えを深めていた。
現時点で氏が送り出す作品として、これは成功なのだと思う。
実はこの作品が上梓されて以降、氏のライブを観ていない。
人づてにライブパフォーマンスにも変化がありこれまで以上に聴くものを圧倒するものだという。
観ねばならない。
年内にまたマイ・シャトーに呼びたいと思う。